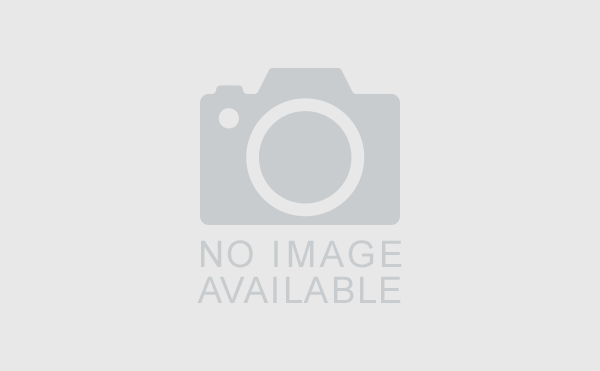パワハラの正体~ 自分の常識 vs 相手の非常識 ~
仕事には、それぞれのスタイルがある。
仕事の進め方、価値観、成果の基準——。
それらは、いつの間にか「これが普通」「これが正しい」という自分の常識になっていることが多い。
だからこそ、こう思う瞬間がある。
「なんでこんなこともできないのか?」
「なぜこれが当たり前だと思わないのか?」

違和感が生まれ、イライラし、怒りへと変わる。
そして、その怒りが積み重なったとき、何が起こるか。
それが今の時代では「パワハラ」と呼ばれるものなのかもしれない。
パワハラとは?
厚生労働省の定義によると、パワーハラスメント(パワハラ)とは、
「職場での優越的な関係を背景に、業務上適正な範囲を超えて、他者に精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」とされている。
具体的には、次のような行為が該当する。
・「お前は使えない」と人格を否定する発言を繰り返す
・ 明らかに過大または過少な業務を与えて退職に追い込む
・ 必要以上に怒鳴る、威圧する
明らかに不適切な行為だが、これらが起こる背景には、単なる「怒り」や「嫌がらせ」ではなく、
「自分の常識と相手の常識のギャップ」があるのではないかと感じる。
パワハラは時代の問題ではない
「最近の若者は…」「昔はこんなことで怒られなかった」
よく聞く言葉だが、これは今に始まった話ではない。
例えば、江戸時代の武士社会。
主君への忠誠、上下関係の厳格さ、礼儀作法の徹底。
「お前の忠義が足りない」「武士たるもの、切腹して責任を取るべき」
現代ならパワハラどころではないが、当時はこれが「常識」だった。
戦時下の日本もそうだ。
「命をかけて国に尽くすのが当然」
その価値観のもと、「気合が足りない」「根性を見せろ」という指導が当たり前だった。
そして、それは戦後の企業文化にも引き継がれた。
昭和のサラリーマンたちは上司の命令に絶対服従。
「飲み会に来ないやつは会社の一員とは言えない」
「長時間働くことこそ、会社への忠誠心」
こんな価値観が横行していた。
今の基準で見れば、これらはすべて「パワハラ」と認定されてもおかしくないものばかり。
しかし、当時の人々にとっては、これが「常識」だった。
結局、パワハラとは「常識 vs 非常識」の衝突から生まれるものなのではないか。
なぜ「常識のギャップ」は怒りを生むのか?
・「努力すれば結果が出る」と信じている人は、努力しない人にイライラする
・「仕事は厳しくて当然」と思っている人は、甘い環境にいる人を許せない
・「自分はこうやって成長してきた」と信じている人は、それをしない人を否定する
これは、誰にでも起こりうること。
そして、このギャップが強ければ強いほど、怒りも大きくなる。
結果、それがパワハラにつながる。
実際、パワハラは上司が部下に対してだけでなく、部下が上司に対して「なんでこんなこともできないのか」と苛立つこともある。
時代や環境が変わるほど、「自分の常識」が通じなくなる場面は増えていく。
パワハラを回避するには?
この「常識 vs 非常識」の衝突を回避する方法を考えてみた。
- 「自分の常識は、あくまで“自分のもの”と理解する
自分にとっての正義やルールが、他人にとっても同じとは限らない。
「なぜこうしないのか?」と感じたら、まず「そもそも自分の前提が違うのでは?」と疑ってみる。 - 相手の「背景」を知る
価値観は、その人が経験してきた環境に大きく左右される。
例えば、新卒から同じ会社で育ってきた人と、転職を繰り返している人では、仕事のスタイルが違って当然。
「なぜ、そう思うのか?」を対話の中で探るだけで、見え方が変わることもある。 - 「結果が出ていればOK」と割り切る
細かいやり方や過程ではなく、「結果」にフォーカスする。
自分のやり方と違っても、相手が結果を出せるなら、それでいいと考える。
無駄なストレスも減るし、相手にとってもプレッシャーにならない。
結局のところ
パワハラとは、時代によって名前を変えながら、人間社会のどこにでも存在する「常識の衝突」なのではないか。
「なんでこんなこともできないんだ?」
「こうするのが当たり前なのに」
そう思ったら、一度立ち止まること。
それは、本当に「相手の問題」なのか?
もしかすると、自分の「常識」がずれているだけかもしれない。