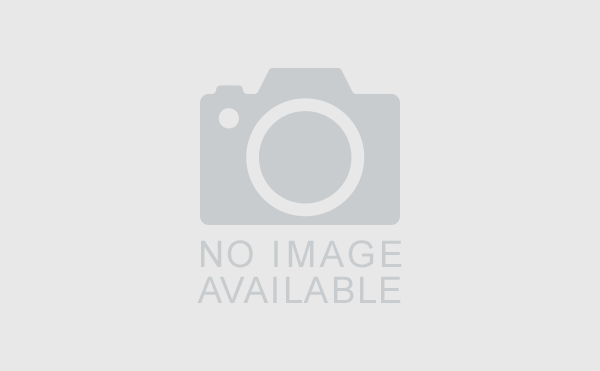昭和・平成の働き方 vs. 現代の職場—今では非常識な昔の常識
📌 「飲み会強制・長時間労働・年末年始の休みは上司次第」…今ならどうなる?

「昔はよかった」と言う人がいる。
でも、本当にそうだろうか?
今では考えられない昭和・平成の職場文化。
当時は“当たり前”だったが、現代の感覚では“非常識”なエピソードを振り返り、なぜそうだったのか、今の時代にどう活かせるのかを考えてみたい。
📌 今では信じられない!?昭和・平成の職場のリアルな光景
✅ 1. 飲み会は仕事の一部。「断る=協調性がない」
昭和・平成の時代、「飲み会は仕事の延長」 という考えが根付いていた。
🔹 実際にあった話
ある40代の営業マンが新卒時代、金曜の夜に先輩から「おい、新人。今日は何時から飲める?」と聞かれた。
「すみません、友人と約束があるので…」と答えた瞬間、場の空気が凍った。
すると上司が一言、「お前、会社の人間関係より大事な約束があるのか?」
その後、新人の彼は「付き合いが悪い」「仕事を舐めてる」と陰で言われることになったという。
☑ 現代では?
・ 業務時間外の飲み会は自由参加が基本
・ むしろ、無理強いするとパワハラ扱い
✅ 2. 長時間労働=頑張っている証拠
「遅くまで働く=仕事熱心」という価値観は根強かった。
効率よく終わらせて定時で帰ると、なぜか評価が下がる。
🔹 実際にあった話
かつての日本企業では、「定時で帰る人はやる気がない」と評価された。
あるメーカー勤務の社員が、17時に仕事を終えたので帰ろうとすると、隣の席の先輩が声をかけてきた。
「お前、今日は何かあったのか?」
「えっ、特に何もないですけど…」と答えると、
「じゃあもうちょっと残れよ。周り見ろよ、みんなまだ働いてるだろ?」
仕事が終わっても、上司や同僚が帰らない限り、帰れない。
"気を遣う文化"が長時間労働を生み出していた。
☑ 現代では?
・ 「長時間労働=評価が上がる」ではなく、「成果で評価」が基本
・ 残業が常態化している職場は敬遠されがち
✅ 3. 年末年始の休みは、上司の気分次第
今では考えられないが、昭和・平成の時代、年末年始の休みが「会社のルール」ではなく「上司の裁量」で決まることがあった。
🔹 実際にあった話
ある金融機関では、「年末年始の休みの日程」が正式に発表されるのが12月中旬だった。
それまで誰も休みが確定しない。なぜなら、部長の一存で決まるから。
ある年、部長が突然こう言った。
「俺は31日まで出社するから、お前らも出られるよな?」
…いや、そんなの聞いてない。
部下たちは、「帰省の予定を入れてしまった」とは言えず、結局、大半が31日まで出社したという。
☑ 現代では?
・ 企業ごとに決められた休暇ルールが存在
・ 有給休暇の取得が推奨され、ワークライフバランスを重視する流れに
📌 昭和・平成の働き方、今の時代に活かせることは?
ここまで、昔の働き方の"非常識"エピソードを紹介してきたが、すべてが悪かったわけではない。
昔の職場文化にも、現代に応用できる「良い部分」もあった。
✅ 1. 「飲み会は仕事の一部」→ 風通しの良い職場づくりへ
飲み会の強制は論外だが、「職場の人とオフで話す時間は大事」 というのは事実。
今の時代は、気軽なランチミーティングや、オンライン雑談 などに進化させてもいいかもしれない。
✅ 2. 「長時間労働が美徳」→ 時間管理の意識
長く働けばいい時代は終わったが、「時間の使い方を意識する」ことは大事。
「生産性を上げる」「メリハリをつける」といった働き方は、昭和・平成の反省を活かした結果とも言える。
✅ 3. 「年末年始の休みは上司次第」→ 休みの計画的な取得
昔の「休みが決まらない」時代を考えると、現代の「有給推奨」「ワークライフバランス重視」の流れは大きな進歩。
せっかく決まった休みなら、有意義に過ごしたいものだ。
📌 今の働き方が"非常識"にならないように
✅ 昭和・平成の職場文化は、現代では非常識なものが多い
✅ ただし、良い部分もあり、それを活かすことが大事
✅ 今の"常識"も、未来の"非常識"になる可能性がある
「昔はこうだった」「今の若い人は…」と昔の価値観を押し付けるのではなく、時代に合わせて柔軟にアップデートしていくことが大切だと思います。それは今を生きる令和の我々も例外ではないと思います。