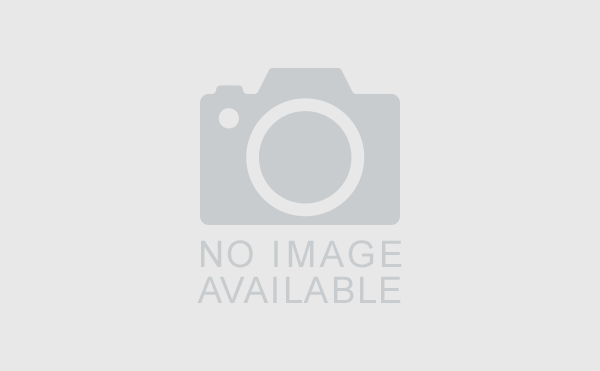スポーツ選手はなぜ引退後に苦労するのか?—キャリアの寿命を考える
📌 どの職業にも「ピーク」はある。セカンドキャリアの作り方

(本投稿で使用している画像は、内容を象徴するイメージとして選定したものであり、特定の団体・個人・事例とは一切関係ありません。)
「引退後の人生、どうする?」
プロスポーツ選手の引退後の苦労話は、珍しくありません。
華やかな舞台で活躍したアスリートが、引退後に仕事を見つけられずに苦労する。そんなニュースを目にするたびに、「どうして?」と思う人も多いのではないでしょうか。
しかし、これは決してアスリートだけの問題ではありません。
営業職でも、エンジニアでも、経営者でも、どの職業にも「ピーク」はあります。
では、なぜスポーツ選手は引退後に苦労しやすいのか?
そして、どうすれば「セカンドキャリア」をスムーズに築けるのか?
今回は、スポーツ選手のキャリアを通じて、どの職業にも共通する「キャリアの寿命」と、その先の生き方について考えてみます。
スポーツ選手の引退後の現実—なぜ苦労するのか?
プロ選手の現役寿命は短く、例えばサッカーや野球のトップ選手でも30代半ばで引退するケースが一般的。
中には20代で引退する選手も少なくありません。
では、引退後の選手たちはどうなるのか?
✅ 成功するパターン
指導者になる(監督・コーチ・育成スタッフ)
スポーツ関連の仕事に就く(解説者・スポーツビジネス)
起業する(ジム経営・ブランド立ち上げ)
⛔ 苦労するパターン
専門スキルがスポーツに偏りすぎている
ビジネスの経験や人脈がない
現役時代の収入に頼りすぎていた
たとえば、ある元プロ野球選手は、引退後に飲食店を開業したものの、経営の知識が不足していて失敗。
貯金が尽きてしまい、生活に困窮するケースもあります。
スポーツ選手の引退後の苦労は、「次のキャリアをどう築くか?」を現役時代から考えていなかったことに原因があることが多いのです。
これは「普通のキャリア」にも当てはまる話
この話、実はスポーツ選手だけのものではありません。
・営業職→管理職になったが、マネジメントが合わず行き詰まる
・エンジニア→技術が陳腐化し、40代で転職に苦戦する
・経営者→会社を売却後、次のキャリアを見つけられない
どの職業にも「キャリアのピーク」があり、その先の戦略がなければ、いずれ苦労する可能性があります。
だからこそ、セカンドキャリアの準備が重要になってきます。
セカンドキャリアを成功させるための3つのポイント
では、どうすれば「キャリアの寿命」を延ばし、スムーズに次のステージへ移行できるのか?
スポーツ選手だけでなく、一般のキャリアにも応用できる3つのポイントを紹介します。
①現役のうちから「次のキャリア」を意識する
アスリートは、現役のうちに指導者の資格を取るケースが増えている
会社員も、「今の仕事がなくなったらどうする?」を常に考えておく
②スポーツ以外(本業以外)のスキルを身につける
実際、プロ野球選手の中には、MBAを取得している人もいる
ITエンジニアなら、マネジメントや営業のスキルを学んでおく
③人脈を広げる(異業種とのつながりを持つ)
解説者として活躍する元アスリートは、現役時代からメディアとの接点を持っていたケースが多い
会社員も、社内だけでなく、外部のコミュニティや異業種交流を大事にする
これからの時代、キャリアは一つではない
かつては「1社に勤め上げる」「1つの仕事を続ける」ことが当たり前でした。
しかし、今の時代は違います。
・スポーツ選手がビジネスの世界に転身する
・会社員がフリーランスとして独立する
・営業職がマーケティングやITにキャリアチェンジする
今の仕事が「ずっと続く」と思わず、次のキャリアの可能性を探してみることが、長く活躍する秘訣かもしれません。
「今の仕事がなくなったら?」
そんな視点で、自分のキャリアを見直してみてもいいかもしれません。